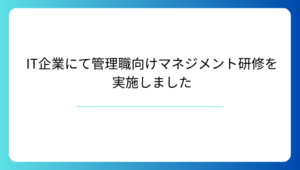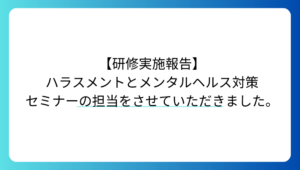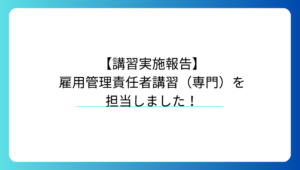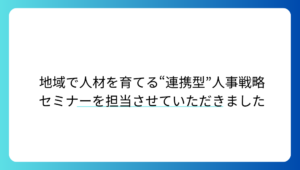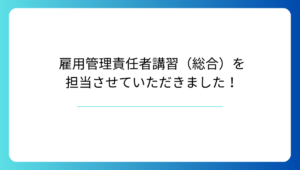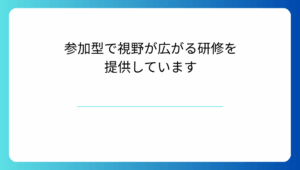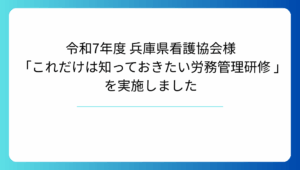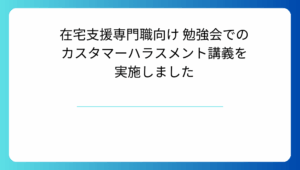介護現場で求められる接遇力とは?
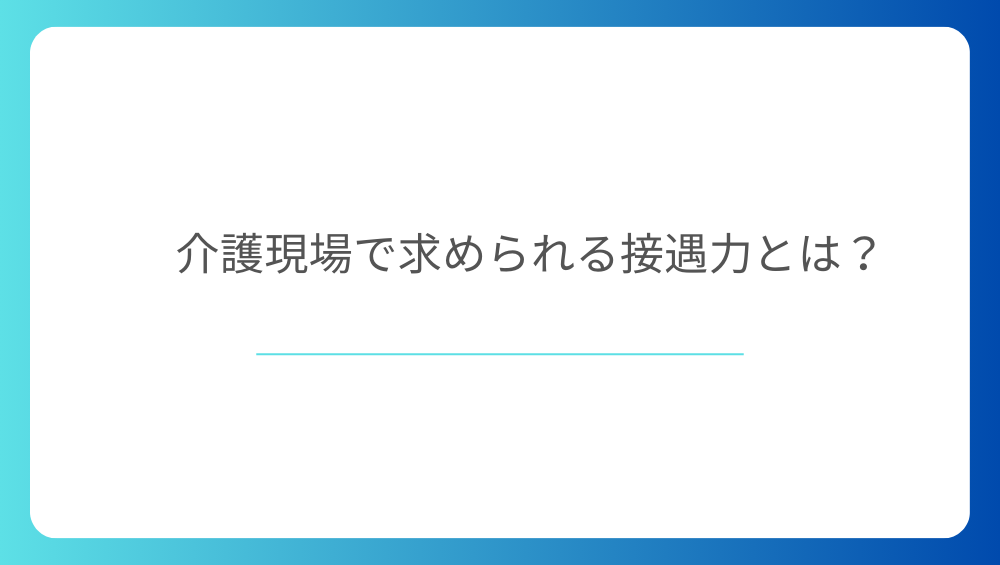
ある介護事業所様より、接遇マナー研修のご依頼をいただきました。
本研修は、法定研修の一環として実施されることも多く、加えて、ご利用者様に対して“なれなれしい”態度にならないよう、丁寧で安心感のある接遇を実現することを目的に、導入されるケースが増えています。
接遇とは「マインド」と「スキル」の両輪です
私たちは接遇を、単なるマナーではなく、「おもてなしの心を持って相手に接する」ことと捉えています。
- マインド:相手の気持ちを理解しようとする姿勢
- スキル:その気持ちを適切に伝えるための言葉遣いや表現力
特に介護現場においては、接遇マナーは信頼形成とチームケアの基盤となるものであり、感覚だけに頼らず、体系的に学ぶことが重要です。
マインドを支える専門職としての責任
研修では、介護職として知っておくべき以下のような倫理的・法的視点もあわせてお伝えします。
- 介護労働の誠実遂行義務
- 守秘義務および個人情報保護義務
たとえば、「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」が大切とはいえ、守秘義務や個人情報保護の意識がなければ、意図せず情報漏洩につながる危険性があります。
介護職は、常にセンシティブな情報を取り扱っているという自覚が求められるのです。
よかれと思った行為が、チームを乱すことも
介護はチームワークで行われるものです。
例えば、利用者から「ペットに餌をあげてほしい」と頼まれ、個人の判断で対応してしまうと、
- 他の職員が対応しなかった場合に利用者が不満を感じる
- 「あの人じゃないと対応してもらえない」と特定の職員への依存が生まれる
- 結果としてシフトが回らなくなる、という問題に発展することもあります。
良かれと思った対応が、事業所全体の統率や運営に支障をきたす可能性があるという点も、接遇研修でしっかりと共有します。
言葉遣いも大切なポイントです
たとえば、親しみやすくしようと「○○ちゃん」と呼んでいたとしても、利用者によっては「なれなれしい」と不快に感じることもあります。
話し言葉の使い方も含めて、一人ひとりのニーズに応じた丁寧な関わり方を学ぶことが、信頼関係の構築につながります。
ご希望に応じて、研修内容を柔軟にカスタマイズ
本研修は、介護現場の状況やご要望に応じて、内容を調整・カスタマイズして実施いたします。
接遇の基本から、実際の現場での具体的なケーススタディまで、現場で本当に役立つ内容を提供いたします。まずはお気軽にご相談ください。