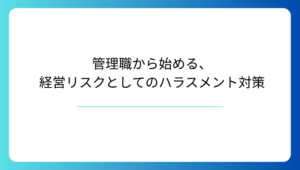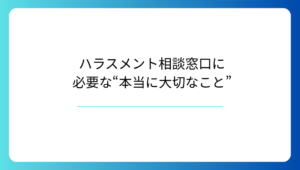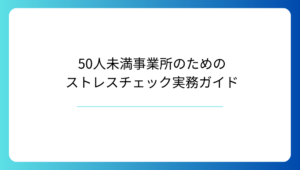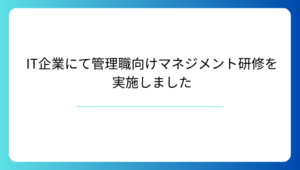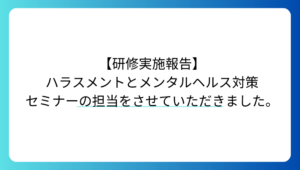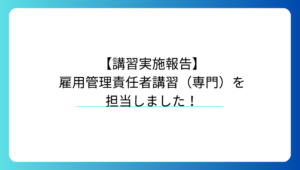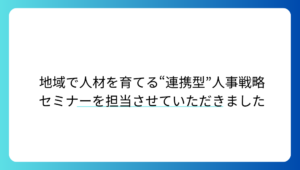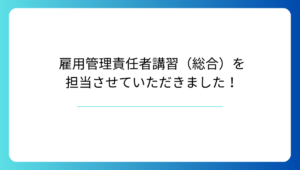ラインのケアとは何か、ご存知ですか?
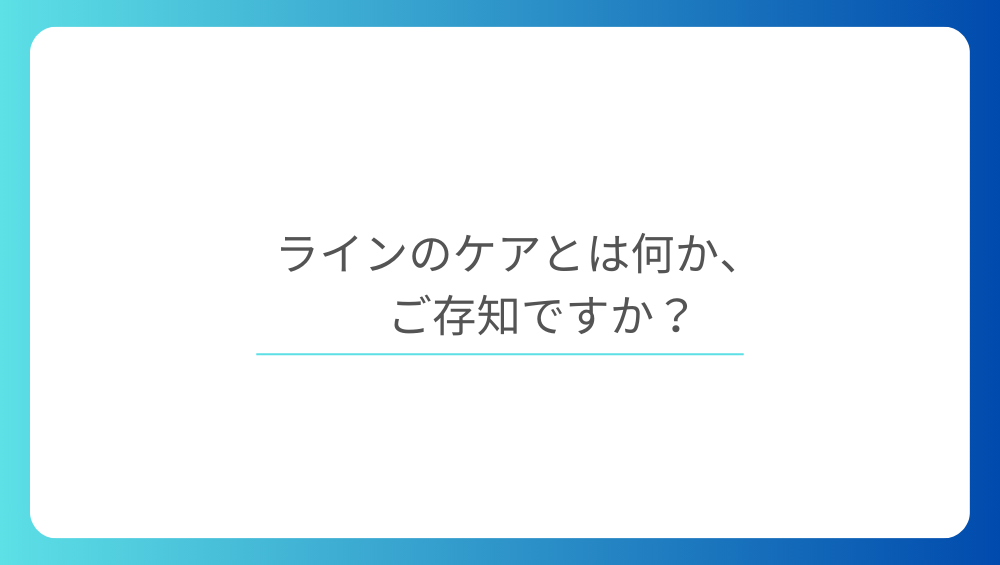
ラインのケアとは何か、ご存じですか?
ラインのケアとは、上司(ライン管理者)が日常的に部下の健康状態に目を配り、「いつもと違う」と感じたときに声をかけ、必要に応じて産業医や医療機関につなぐことを指します。
もちろん、基本は本人が自ら医療機関を受診する「自己受診義務」があります。しかし、真面目で責任感の強い部下ほど、「自分が頑張れば何とかなる」と無理をしてしまい、自ら助けを求められないことも少なくありません。
実際の企業でのケース
ある企業では、パートを含めて約30名の職員が在籍しています。その中にはPTSDを抱えている従業員もおり、過去にはメンタル不調によって離職に至ったケースもありました。このような背景から、「ラインのケア」について研修のご依頼をいただきましたが、ご担当者様はその言葉自体をご存じではありませんでした。
研修では、ラインのケアとは何か、上司としてどのように行動すべきかを丁寧にお伝えし、メンタル不調の兆しが見られる部下に対しては、まず声をかけ、話をよく聴き、必要に応じて医療機関につなぐことの重要性を共有しました。
また、かかりつけ医では対応が難しい場合には、セカンドオピニオンを活用することも一つの選択肢であることもお伝えしました。
ラインのケアの基本 ― 「3L」の実践
部下のメンタルヘルスを守るために、上司ができること。
その行動の基本が、次の「3L」です。
Look(見る)
日常の中で、部下の様子に「いつもと違う」サインがないかを観察します。
- 表情が暗い
- 遅刻が増えている
- 業務ミスが目立つ
- 話しかけづらい雰囲気がある
こうした小さな変化を見逃さないことが第一歩です。
Listen(聴く)
気になる様子があれば、タイミングを見て声をかけ、じっくり話を聴くことが大切です。判断やアドバイスよりも、まずは「聴く姿勢」が信頼を築きます。
「最近、元気がないように見えるけど、大丈夫?」といった一言の声掛けがきっかけになります。
Link(つなぐ)
話を聴いた結果、「これは一人では抱えきれない」と感じたら、産業医や医療機関、社内の相談窓口につなぐことが管理職の重要な役割です。本人の判断だけに任せず、必要な支援への“橋渡し”を行いましょう。
管理職が知っておきたい心構え
- 「頑張れば何とかなる」と無理をしてしまう部下ほど、早めの声かけが必要です。
- メンタル不調は目に見えにくく、本人も相談しづらいものです。
- 上司からの気づきと一言が、早期対応と職場定着につながります。
- かかりつけ医では対応しきれない場合には、セカンドオピニオンの活用も視野に入れましょう。
まずは「ラインのケア」を知ることから始めませんか?
ラインのケアが必要な場面であっても、そもそもラインのケアとは何かがわからなければ、どのように対応すべきか判断できません。だからこそ、「ラインのケアとは何か」「どんな場面でどう実践するのか」を正しく理解することが重要です。当事務所では、現場で実践できるラインのケア研修をご用意しています。
「自社にはどんな研修が合うのか」「何から始めればよいのか」など、まずはお気軽にお問い合わせください。
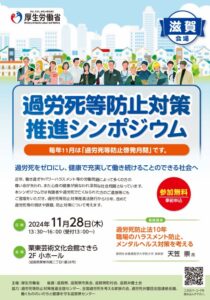
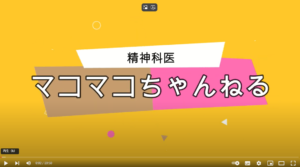
セミナー・研修・講演

リーダー育成、メンタルヘルス、ハラスメント防止、採用と定着等、ニーズに対応した実践型研修を提供します。
コンサルティング

採用支援、ホワイト財団、介護や福祉の処遇改善加算、就業規則、ハラスメント防止等のコンサルティングを行います。
著書・執筆

著書の執筆、雑誌への寄稿・監修、リーフレット原稿の作成を行います。また専門家としてインタビューにも応じます。